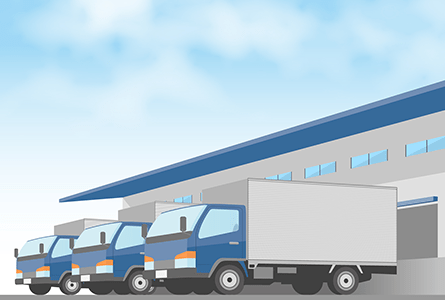
چ‚‘¬“¹کH‚ً‘–‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ئپA–ع‚ة‚·‚邱‚ئ‚ج‘½‚¢‘هŒ^•¨—¬ژ{گفپB
‚ ‚؟‚±‚؟‚إŒ©‚é‚ج‚إپu‚±‚ٌ‚ب‚ة‚àژù—v‚ھ‚ ‚é‚ج‚©پv‚ب‚ا‚ئژv‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚¢‚ـ‚·‚ھپAŒ»‘م‚ج”ƒ‚¢•¨ƒXƒ^ƒCƒ‹‚â‚ذ‚ء”—‚µ‚ؤ‚¢‚镨—¬ڈَ‹µ‚ًٹس‚ف‚ê‚خپu‚ـ‚¾‚ـ‚¾‘‚¦‚»‚¤پv‚ئ‚¢‚¤ژv‚¢‚à‚و‚¬‚è‚ـ‚·پB
چ،‰ٌ‚ح•¨—¬•s“®ژY‚جŒ»ڈَ‚ة‚آ‚¢‚ؤ‰ًگà‚µ‚ـ‚·پB
•¨—¬Œn•s“®ژY‚ج•د‘J
•¨—¬Œn•s“®ژY‚ئ‚¢‚¦‚خپA‚©‚آ‚ؤ‚ح‡@ژ©ژذ‚إ•غ—L‚·‚é‘qŒة ‡A‘qŒة‹ئژز‚ھ•غ—L‚·‚é‘qŒة‚ج2ƒpƒ^پ[ƒ“‚إپA‚¢‚ـ‚إ‚à‡@‡A‚ئ‚à‘½‚Œ©‚ç‚ê‚ـ‚·پB
‡@‚حژ©ژذ•غ—Lژ©ژذ—ک—p‚جƒpƒ^پ[ƒ“‚إپA‡A‚ح‰×ژهپiٹé‹ئپj‚©‚çˆد‘ُ‚³‚ê‚é‰ف•¨‚ً•غٹا‚·‚é‚ئ‚¢‚¤ژù—v‚ة‰‚¦‚é‚à‚ج‚إ‚·پB
‚µ‚©‚µپAƒTƒvƒ‰ƒCƒ`ƒFپ[ƒ“‚ًچإ“K‰»‚·‚邱‚ئ‚ًٹé‹ئ‚ح‹پ‚ك‚ç‚êپA‚»‚ê‚ة‘خ‰‚·‚镨—¬ژ{گف‚ھ•K—v‚ئ‚ب‚èپA‚ـ‚½•¨—¬ƒRƒXƒg‚ًچيŒ¸‚µ‚½‚¢‚ئ‚¢‚¤ژvکf‚ھچL‚ھ‚è‚ـ‚·پB ‚»‚ج‚½‚كپAچ‚‹@”\‚ب•¨—¬ژ{گف‚ھ‹پ‚ك‚ç‚ê‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚è‚ـ‚µ‚½پB
‚³‚ç‚ة•¨—¬‚ًژو‚èٹھ‚ٹآ‹«‚ًٹس‚ف‚ê‚خپAگlŒûŒ¸ڈپEڈژqچ‚—‚جگi“W‚ة‚و‚éکJ“—ح•s‘«‚جŒ°چف‰»پAچ‘چغ‹£‘ˆ‚جŒƒ‰»پAڈî•ٌ’تگM‹ZڈpپiICTپj‚جٹvگV‚ب‚اپA‹ك”N‘ه‚«‚•د‰»‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
‚±‚ê‚ة”؛‚¢•¨—¬‚ة‘خ‚·‚é‰×ژه‚âڈء”ïژز‚جƒjپ[ƒY‚ھ‘½—l‰»‚µ‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚ة‚و‚èپA•¨—¬ژ{گف‚ة‘خ‚·‚éƒjپ[ƒY‚àژ‘م‚ئ‚ئ‚à‚ة•د‘J‚ً‚½‚ا‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
•¨—¬•s“®ژY‚ئ‚ح
‚±‚ج‚و‚¤‚ب”wŒi‚ج’†‚إپA’ہ‘فŒ^•¨—¬ژ{گفپiپپپu•¨—¬•s“®ژYپv‚ئŒؤ‚خ‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پj‚ھ‘‚¦‚ؤ‚«‚ـ‚µ‚½پB
REITپiReal Estate Investment TrustپF•s“®ژY“ٹژ‘گM‘ُپj‚ج‘nگف‚ب‚اپA•s“®ژY“ٹژ‘‚جٹآ‹«‚ھگ®”ُ‚³‚ꂽ‚±‚ئ‚ًژَ‚¯‚ؤپA‘qŒة‹ئگê‹ئ‚إ‚ح‚ب‚چ‘“àٹO‚ج•s“®ژY‰ïژذ‚âƒnƒEƒXƒپپ[ƒJپ[‚ب‚اپA‘½‚‚جƒvƒŒƒCƒ„پ[‚ھژQ‰و‚·‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚è‚ـ‚µ‚½پB
•¨—¬•s“®ژY‚ئ‚حپu•¨—¬‹ئ–±‚ًچs‚¤‚½‚ك‚جژ{گف‚ئ‚µ‚ؤٹé‹ئ‚ب‚ا‚ج‘وژOژز‚ض’ہ‘ف‚³‚ê‚é‘qŒةپE•¨—¬ƒZƒ“ƒ^پ[“™‚جŒڑ•¨پv‚ج‚±‚ئ‚ًŒ¾‚¢‚ـ‚·‚ھپA‚»‚ج‘½‚‚حƒ}ƒ‹ƒ`ƒeƒiƒ“ƒgƒ^ƒCƒv‚إˆê”ت“I‚ب‘qŒة‚ة”ن‚ׂؤ‘ه‚«‚بژ{گف‚ئ‚ب‚è‚ـ‚·پB
“¯‚¶‚و‚¤‚ب—ک—p‚ً‚³‚ê‚é‘qŒة‚ح—A‘——ت‚â•غٹا—؟‚ة‰‚¶‚ؤ—؟‹à‚ھ”گ¶‚µ‚ـ‚·‚ھپA•¨—¬•s“®ژY‚إ‚حƒIƒtƒBƒXƒrƒ‹‚ج‚و‚¤‚ة’ہ‘ف–تگد‚ة‰‚¶‚½’ہ—؟‚ھ”گ¶‚·‚é“_‚إˆظ‚ب‚éƒAƒZƒbƒg‚ئŒ¾‚¦‚ـ‚·پB
‰×•¨‚ًˆµ‚¤ٹé‹ئ‚ج—§ڈê‚ة—§‚ؤ‚خپA‡@ژ©ژذ‚إ‘qŒة‚ً•غ—L‚·‚é ‡A‘qŒة‚ًژط‚è‚é ‡B•¨—¬•s“®ژY‚ًژط‚è‚é ‚ج3‚آ‚ج‘I‘ًژˆ‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·‚ھپA‡@‚جڈêچ‡‚ح—p’n‚âŒڑ’z”ï—p‚ب‚ا‚جڈ‰ٹْ“ٹژ‘‚ھ‚©‚©‚é“_‚إپA‡A‡B‚ج‘I‘ًژˆ‚ً‘I‚شٹé‹ئ‚ھ‘‚¦‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
’ہ‘ف•¨—¬ژ{گفپF•¨—¬•s“®ژY‚ج’êŒک‚¢ژù—v‚ج”wŒi
‰ك‹ژ‚ًگU‚è•ش‚é‚ئپA‰×ژه‚©‚çˆث—ٹ‚³‚ê‚é‰ف•¨‚ج•غٹا‚ًژه‚بژ–‹ئ‚ئ‚·‚é‘qŒةپuپپ•غٹاŒ^‚ج•¨—¬ژ{گفپv‚ھژه—¬‚إ‚µ‚½‚ھپA1990”N‘مŒم”¼‚©‚ç‰ف•¨‚ج•غٹا‚¾‚¯‚ة‚ئ‚ا‚ـ‚炸ƒRƒXƒgچيŒ¸‚âƒTƒvƒ‰ƒCƒ`ƒFپ[ƒ“‚جچإ“K‰»‚ئ‚¢‚ء‚½‰×ژهƒjپ[ƒY‚ة‘خ‰‚µپAچ‚‹@”\‚بگف”ُ‚ج“±“ü‚â—¬’ت‰ءچHƒXƒyپ[ƒX‚جٹm•غ‚ب‚اپA•غٹاˆبٹO‚ج•t‰ء‰؟’l‚ً‚آ‚¯‚½پu”z‘—Œ^•¨—¬ژ{گفپv‚ض‚جˆعچs‚ھگi‚ف‚ـ‚µ‚½پB
”wŒi‚ئ‚µ‚ؤ‚حپA
‡@ECژsڈê‚ھ‹}ٹg‘ه‚µ‘î”z•ضژوˆµگ”‚ھŒƒ‘‚µ‚½‚±‚ئ
‡AƒRƒ“ƒrƒjژsڈê‚جٹg‘ه‚ئƒRƒ“ƒrƒj‹@”\‚ًچ‡‚ي‚¹‚à‚آƒhƒ‰ƒbƒOƒXƒgƒA‚جژsڈê‚ھٹg‘ه
→’·ژٹش‰c‹ئ‚©‚آ“sژs•”“X•ـ‚ھ‘½‚‘qŒةƒXƒyپ[ƒX‚ھ‹·‚¢‚½‚كپA1“ْگ”‰ٌ‚ج”z‘—‚âڈ¬Œûƒچƒbƒh‚إ‚ج”z‘—‚ھژه‚ئ‚ب‚èپA•¨—¬‹@”\‚جŒّ—¦‰»‚ھ•Kگ{‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
‡B‹Œ—ˆ‚ج•¨—¬ژ{گف‚جکV‹€‰»‚ھگi‚ٌ‚إ‚¢‚邱‚ئ
‡C•¨—¬‹@”\‚ًٹO’چ‚·‚é‚RPLپiƒTپ[ƒhƒpپ[ƒeƒBƒچƒWƒXƒeƒBƒNƒXپjژsڈê‚ھٹg‘ه‚µ‚ؤ‚¢‚邱‚ئ
‚ب‚ا‚ھ‹“‚°‚ç‚ê‚ـ‚·پB
•¨—¬•s“®ژY‚ج‹َژ؛—¦
ژٌ“sŒ—‚âٹضگ¼Œ—‚جچ‚‘¬“¹کH‚ً‘–‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ئ‚و‚Œ©‚©‚¯‚é‘هŒ^•¨—¬ژ{گف‚ج‘½‚‚حJ-REIT–ء•؟‚ة‘g‚فچ‚ـ‚ê‚ؤ‚¢‚镨—¬•s“®ژY‚إ‚·پB
Œ»چف•¨—¬ŒnREIT‚ح8–{پi‘S‘ج‚إ57–{پj‚ ‚è‚ـ‚·پB
‚±‚ê‚ç‚جIRژ‘—؟‚ً‚ف‚é‚ئٹeREIT‚ةچ·‚ح‚ ‚è‚ـ‚·‚ھپAژٌ“sŒ—‚ج•¨—¬•s“®ژY‚ج‹َژ؛—¦‚ح‚¨‚¨‚و‚»10%‘م‘O”¼پ`ˆêŒ…Œم”¼پAٹضگ¼Œ—‚ح5پ“‚ًگط‚éگ…ڈ€‚إگ„ˆع‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
چإ‚à’ل‚©‚ء‚½‚ج‚حپA2019”N‚²‚ë‚©‚ç‚ج”ڑ”“I‚بECژù—v‚ًژَ‚¯‚½2020”Nپ`2021”N‚إپA‚»‚جŒم2022”Nچ ‚©‚ç‹َژ؛—¦‚حڈمڈ¸ŒXŒü‚ة‚ ‚è‚ـ‚µ‚½‚ھپA‚±‚ج‚ئ‚±‚ë‚ح‰،‚خ‚¢‚ئ‚¢‚¤ٹ´‚¶‚إ‚·پB
ڈم‹L‚ج”wŒi——R‡@پ`‡C‚حپAˆّ‚«‘±‚«“–‚ؤ‚ح‚ـ‚邽‚كژù—v‚ة‘ه‚«‚ب•د‰»‚ح‚ب‚¢‚ئژv‚ي‚ê‚ـ‚·پB
‚µ‚©‚µ‚»‚جˆê•û‚إپA2021”Nˆبچ~‚حگV‹K•¨Œڈ‚ج‹ں‹‹‚ھ‘½‚©‚ء‚½‚ج‚ھ‰e‹؟‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ئŒ©ژَ‚¯‚ç‚ê‚ـ‚·پB
‚»‚ج‚½‚كپA”NŒژ‚جŒo‰ك‚ة”؛‚¢‹َژ؛—¦‚ح—ژ‚؟’…‚¢‚ؤ‚‚é‚à‚ج‚ئگ„‘ھ‚³‚ê‚ـ‚·پB
‚»‚ج“_ٹضگ¼Œ—‚ب‚ا‚إ‚حپAگV‹K•¨Œڈ‹ں‹‹‚ھڈ‚ب‚©‚ء‚½‚½‚ك‹َژ؛—¦‚ھڈمڈ¸‚µ‚ؤ‚¢‚ب‚¢‚à‚ج‚ئژv‚ي‚ê‚ـ‚·پB
ûüڈ¼Œڑگف‚ج•¨—¬ژ{گفŒڑ’z
چ‚ڈ¼Œڑگف‚إ‚حپA‚±‚ê‚ـ‚إ‘½‚‚ج•¨—¬ژ{گف‚جŒڑ’z‚ًژèٹ|‚¯‚ؤ‚ـ‚¢‚è‚ـ‚µ‚½پB
ژ©ژذ‚إ•غ—L‚·‚éچHڈê‚ة•¹گف‚·‚镨—¬ژ{گف‚جŒڑ’z‚â‘qŒة‚جŒڑ’zپA‚ـ‚½گو‚ةڈq‚ׂ½‚و‚¤‚بچإگV‚ج’ہ‘ف—p•¨—¬•s“®ژY‚ـ‚إپA‘½—l‚بژ{چHژہگر‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پB
چHڈêپE•¨—¬ƒZƒ“ƒ^پ[‚جژ{چHژہگر‚ح‚±‚؟‚ç
•¨—¬ژ{گف‚حٹO‚©‚猩‚ê‚خپuژlٹp‚¢” پv‚ج‚و‚¤‚ةŒ©‚¦‚ـ‚·‚ھپAپu‚ا‚¤Œّ—¦‚و‚ژg‚¤‚©پv‚ًژ{ژه—l‚ئ‚ج‘إ‚؟چ‡‚ي‚¹‚ًڈd‚ث‚ؤ‚©‚ç‚ج’ٌˆؤ‚حپAژ{چHژہگر‚ھ‘½‚‚ب‚¢‚ئ‚إ‚«‚é‚à‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚ئژv‚¢‚ـ‚·پBچHڈê‚ئ‚ج•¹—p‚جڈêچ‡‚ح‚ب‚¨‚³‚ç‚إ‚·پB
‚ـ‚½ٹù‘¶‚جŒڑ•¨‚جŒڑ‚ؤ‘ض‚¦‚إ‚حپAٹù‘¶•¨Œڈ‚ًژg‚¢‚ب‚ھ‚çŒڑ‚ؤ‘ض‚¦‚µپAƒXƒ€پ[ƒY‚بˆعچs‚ًچs‚¤‚ئ‚¢‚¤“‚³‚à‚ ‚è‚ـ‚·پB ‚±‚¤‚µ‚½‚±‚ئ‚ً’ڑ”J‚ةچs‚¤‚±‚ئ‚àچ‚ڈ¼Œڑگف‚ج“ء’¥‚إ‚·پB‚±‚؟‚ç‚àچ‡‚ي‚¹‚ؤ‚²ٹm”F‚‚¾‚³‚¢پB
‹gچè گ½“ٌپ@Yoshizaki Seiji
‘پˆî“c‘هٹw‘هٹw‰@ƒtƒ@ƒCƒiƒ“ƒXŒ¤‹†‰بڈC—¹پB—§‹³‘هٹw‘هٹw‰@پ@”ژژm‘Oٹْ‰غ’ِڈC—¹پB
پiٹ”پj‘Dˆن‘چچ‡Œ¤‹†ڈٹڈمگبƒRƒ“ƒTƒ‹ƒ^ƒ“ƒgپAReal Estate ƒrƒWƒlƒXƒ`پ[ƒ€گس”CژزپAٹî‘bŒ¤‹†ƒ`پ[ƒ€گس”CژزپAپiٹ”پjƒfƒBپ[ƒTƒCƒ“ژو’÷–ًپ@•s“®ژYŒ¤‹†ڈٹڈٹ’·پ@‚ًŒo‚ؤŒ»گEپB•s“®ژYپEڈZ‘î•ھ–ى‚ة‚¨‚¯‚éƒfپ[ƒ^•ھگحپAژsڈê—\‘ھپAٹé‹ئŒü‚¯ƒRƒ“ƒTƒ‹ƒeپ[ƒVƒ‡ƒ“‚ب‚ا‚ًچs‚¤‚©‚½‚ي‚çپAƒeƒŒƒrپAƒ‰ƒWƒI‚جƒŒƒMƒ…ƒ‰پ[”ش‘g‚ةڈo‰‰پA‚ـ‚½‘Sچ‘گV•·ژذ‚ً‚ح‚¶‚كژه—vƒپƒfƒBƒA‚إ‚جڈµمظچu‰‰‚ح–ˆ”N”Nٹش30–{‚ً’´‚¦‚éپB
پu•s“®ژYƒTƒCƒNƒ‹—ک_‚إ“ا‚ف‰ً‚پ@•s“®ژY“ٹژ‘‚جƒvƒچƒtƒFƒbƒVƒ‡ƒiƒ‹گيڈpپvپi“ْ–{ژہ‹ئڈo”إژذپvپAپu‘هŒƒ•دپ@2020”N‚جڈZ‘îپE•s“®ژYژsڈêپvپi’©“ْگV•·ڈo”إپjپuڈء”ïƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“‚ً”ƒ‚¤گlپAژ‘ژYƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“‚ً‘I‚ׂéگlپvپiگآڈtگVڈ‘پj“™11چûپB‘½گ”‚ج”}‘ج‚ةکAچع‚ًژ‚آپB
ƒŒƒMƒ…ƒ‰پ[ڈo‰‰
ƒ‰ƒWƒINIKKEIپFپu‹gچèگ½“ٌ‚جƒEƒHپ[ƒ€ƒAƒbƒvپ@840پvپu‹gچèگ½“ٌپEچâ–{گT‘¾کY‚جژٹچ‚‚جƒ|پ[ƒgƒtƒHƒٹƒIپv
ƒeƒŒƒr”ش‘gپFBS11‚â“ْŒoCNBC‚ب‚ا‚ج‘½گ”‚ج”ش‘g‚ةڈo‰‰
Œِژ®ƒTƒCƒgپFhttp://yoshizakiseiji.com/





